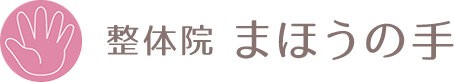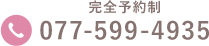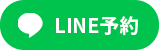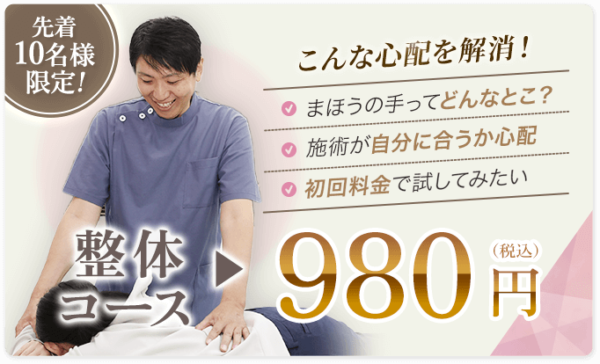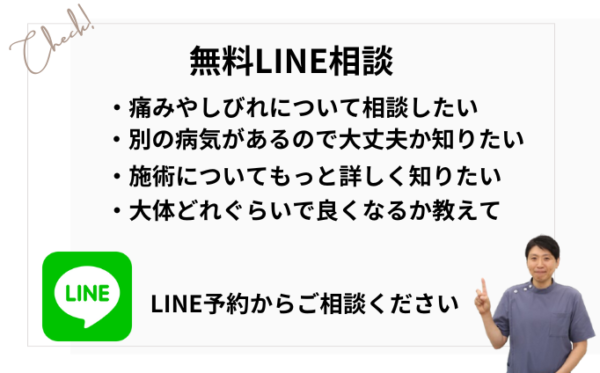階段の昇り降り、筋肉の使い方に違いがあるってホント?
2025年08月31日
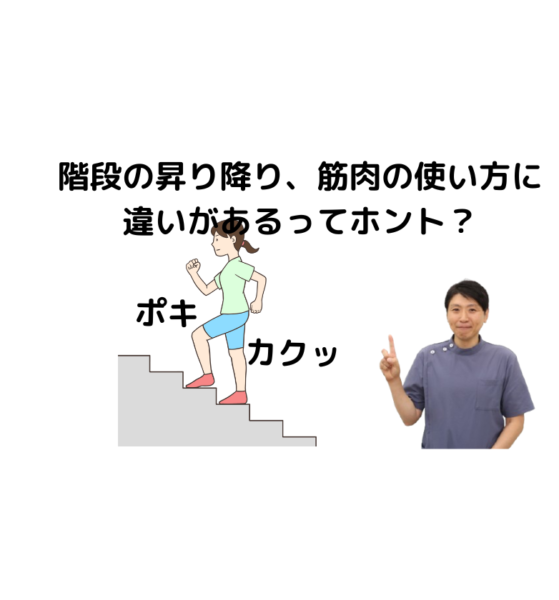
皆さんは、普段何気なく階段を昇り降りしていると思いますが、実はこの2つの動作では、同じ筋肉を使っていても、その働き方には大きな違いがあります。
この違いを理解することで、膝への負担を減らしたり、より効果的に筋力アップを目指したりすることができます。今回は、階段の昇り降りに欠かせない筋肉、大腿四頭筋(太ももの前にある筋肉)に注目して、その働きを分かりやすく解説します。
1. 階段を「昇る」とき
階段を昇るときは、膝を伸ばして体を持ち上げる必要があります。この時に働くのが、筋肉が縮みながら力を発揮する**「求心性収縮」**という動きです。
例えるなら、車のアクセルを踏むようなイメージです。
大腿四頭筋がグッと縮むことで、重力に逆らって体を上に押し上げる推進力を生み出します。階段をスムーズに昇るためには、この求心性収縮をしっかり行うことが大切です。
2. 階段を「降りる」とき
一方、階段を降りるときは、重力に逆らってゆっくりと体を下ろす必要があります。この時に働くのが、筋肉が伸ばされながら力を発揮する**「遠心性収縮」**という動きです。
例えるなら、車のブレーキをかけるようなイメージです。
大腿四頭筋がゆっくりと引き伸ばされながら、膝が勢いよく曲がるのを抑え、体の重さを支えます。この働きが弱いと、膝への負担が大きくなり、関節を痛める原因になることがあります。
まとめ
- 階段を昇る:アクセル(求心性収縮)で体を持ち上げる。
- 階段を降りる:ブレーキ(遠心性収縮)で体を支える。
このように、同じ大腿四頭筋でも、昇るときは**「力を出す」、降りるときは「力を制御する」**という全く異なる役割を担っています。
もし、階段の昇り降りで膝に違和感がある場合は、特に「降りる」ときの筋肉の使い方を見直してみると良いかもしれません。日頃から少しずつ意識して、健康な膝を保ちましょう。
ご予約・お問い合わせはこちらから
整体院まほうの手 公式ホームページ: 大津市 整体院まほうの手
お電話でのご予約: 077-599-4935
LINEでのご予約: LINEはこちら
【整体院まほうの手】
〒520-2134 滋賀県大津市栄町8-30イングビル営業時間: 9:00~21:00(土日祝も営業) 定休日: 不定休