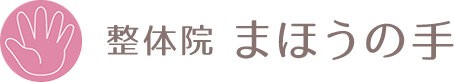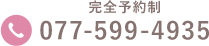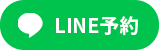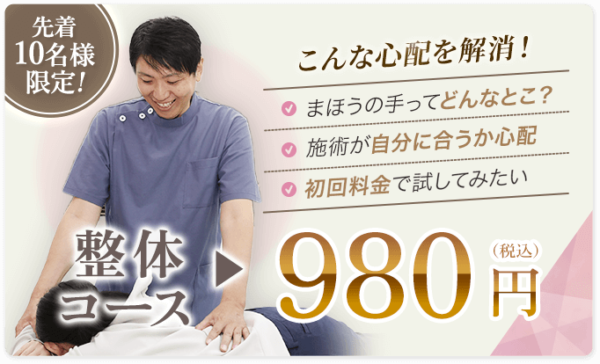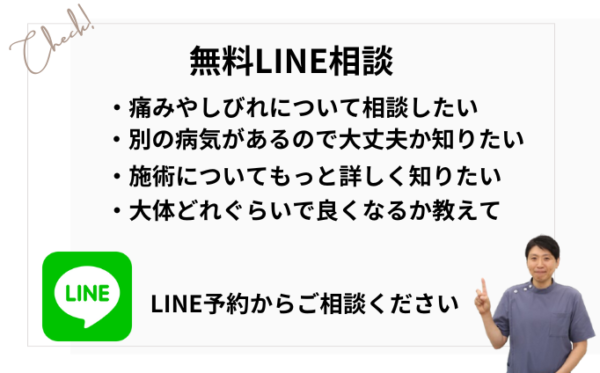「足の外向き」歩行、放置していませんか?〜股関節の変形が招く足関節背屈制限と外反母趾のメカニズム〜
2025年09月29日
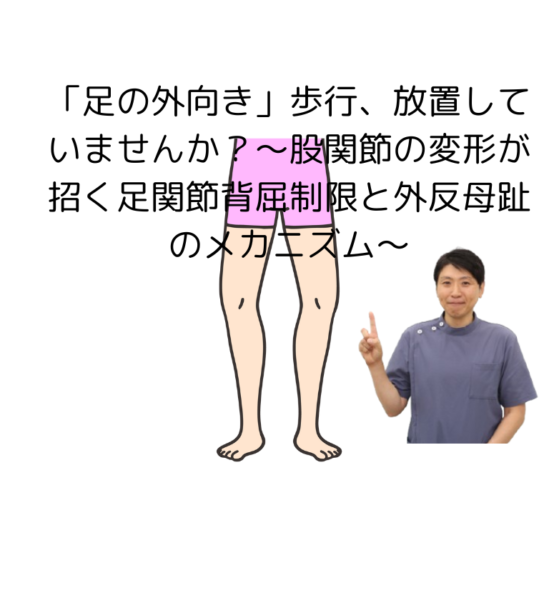
股関節の痛みや違和感があり、自分の歩き方を鏡で見たとき、「なんだか足の先が外を向いているな」と感じたことはありませんか?
変形性股関節症や臼蓋形成不全など、股関節の変形を抱える方に非常によく見られるのが、この**「外旋位歩行」**です。
一見、股関節の問題に見えるこの歩き方が、実はあなたの足首や足の指に深刻な二次的障害を引き起こしていることをご存知でしょうか。
今回は、股関節の変形がどのようにして足の機能に悪影響を与え、背屈制限や外反母趾を促進するのか、そのメカニズムを詳しく解説します。
股関節の「かばい歩き」が足元を壊すメカニズム
股関節の病気がある場合、関節の軟骨がすり減ったり、骨の形が悪かったりすることで、関節の動きが制限されます。特に、脚を後ろに振り出すときの**「股関節の伸展(後ろに伸ばす動き)」**が大きく制限されます。
この「伸展不足」を補い、無理に歩き続けようとするとき、体は以下のような「かばい歩き(代償動作)」を無意識に行います。

1. 股関節を「外旋」させて歩く
股関節を内側にひねる動作(内旋)や伸展(後ろに伸ばす)動作が痛みで制限されるため、股関節全体を外側にひねった(外旋位)状態で歩くようになります。結果として、足のつま先が外を向いたまま着地・蹴り出しを行うことになります。
二次的障害:足関節の「背屈制限」が起こる理由
「背屈」とは、足首を上にそり上げて、すねに近づける動きのことです。
正常な歩行では、地面を蹴り出す直前(立脚後期)に、この背屈の動きが非常に重要になります。効率よく背屈することで、足全体で地面を捉え、次のステップへの力強い推進力を生み出します。
外旋位歩行が背屈を「省略」させる
しかし、足が外を向いた「外旋位」で歩くと、足首の関節軸が不自然な位置にズレてしまい、構造的に効率的な背屈がしにくくなります。
さらに、股関節の動きの悪さを補うために、足関節の背屈を使わずに、足底全体をべったりと地面につけたまま、あるいは足が外側に流れるようにして蹴り出すような**「背屈を回避する歩き方」**が習慣化します。
これにより、足関節の可動域が狭くなり、本来必要な背屈の動きができなくなる**「背屈制限」**が起こります。背屈制限は、歩幅の減少や膝への負担増にもつながります。
二次的障害:外反母趾を「促進」するメカニズム
足が外を向いたまま歩くことで、足の構造にも深刻な負担がかかります。
1. 親指への過度なねじれと集中荷重
外旋位歩行による不自然な蹴り出しは、推進力を生むための力が、足の親指側(母趾)と土踏まずの内側に強く集中してかかってしまいます。
特に、蹴り出しの瞬間に、足には強い**「ねじれ(回内ストレス)」と「外転ストレス」**が生じます。
2. 外反母趾の進行
このねじれと不均衡な荷重が、足の親指の付け根にある関節(MTP関節)に持続的なストレスを与え、外反母趾を進行させる要因となります。
親指の付け根にある骨(第1中足骨)が内側に押しやられ、親指自体が外側に曲がる力が慢性的に加わるため、外反母趾の変形が加速してしまうのです。
この状態を放置すると、外反母趾の悪化だけでなく、土踏まずが崩れる扁平足や、かかとの痛み(足底筋膜炎)など、全身の痛みに発展するリスクも高まります。
股関節と足の連鎖を断ち切るために
股関節の痛みから始まった「外旋位歩行」は、足首、足の指へと連鎖し、体のあちこちに不調を広げてしまいます。
これらの二次的な障害を防ぎ、快適な日常生活を取り戻すためには、以下の対策が重要です。
- 専門医の受診と根本治療: 股関節の変形に対する適切な診断と治療を最優先しましょう。
- 理学療法(リハビリ): 専門家による指導のもと、正しい歩行パターンを再学習し、硬くなった股関節周囲の筋肉のストレッチや筋力強化を行いましょう。
- インソール(足底板)の活用: 足のアーチをサポートし、不均衡な荷重を分散させるオーダーメイドのインソールは、外反母趾や背屈制限の進行を抑えるのに非常に有効です。
「股関節が悪いから仕方ない」と諦めず、足元から全身のバランスを整えていくことが、健康寿命を延ばす鍵となります。専門家と一緒に、あなたの歩き方を見直してみませんか?
ご予約・お問い合わせはこちらから
整体院まほうの手 公式ホームページ: 変形性股関節症 | 大津市 整体院まほうの手
お電話でのご予約: 077-599-4935
LINEでのご予約: LINEはこちら
【整体院まほうの手】
〒520-2134 滋賀県大津市栄町8-30イングビル営業時間: 9:00~21:00(土日祝も営業) 定休日: 不定休